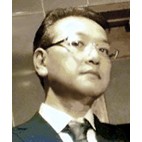ゴールデンウイーク三日目も以下略…..
2011年5月1日 書道で、夢の中でも書道してて、すごくいい書き方思いついて起きちゃったのが4時半…..2時間半しか寝れてないのは、ちょっとだけヒミツだ。肩はアイシングと湿布のおかげで動くようになったし、うんと疲れてもいるが、そういった諸々のモノは心に棚をつくって、しまってしまうのも大事。『心に棚を作れ!』と某島本先生もおっしゃってる事だし。締め切り際なんて、そんなもんそんなもん。
ナゾのハイテンションのまま、寝ぼけて書いた一枚目....(実はここまでで三枚失敗している)は.ムチャクチャに字のデカい代物、当然、ボツ。気を取り直して肘と腕を締め、書いてなんとか7時半までに2枚を仕上げる。書いたものをつるして選別。10枚までに落とし込む。
寝ぼけて練成会に行くわけにはいかないので、シャワーを浴びてドリンク剤を飲んで太無書法研究社へ。
まあ、付け焼刃なのはしょうがないし、地力がないのもしょうがないので、随分拙いものをお見せしてしまった感じで反省する事しきりで….がんばるぞ、おー。
帰宅は16時、そこからばったり爆睡….明日は仕事だっちゅうの…..
ナゾのハイテンションのまま、寝ぼけて書いた一枚目....(実はここまでで三枚失敗している)は.ムチャクチャに字のデカい代物、当然、ボツ。気を取り直して肘と腕を締め、書いてなんとか7時半までに2枚を仕上げる。書いたものをつるして選別。10枚までに落とし込む。
寝ぼけて練成会に行くわけにはいかないので、シャワーを浴びてドリンク剤を飲んで太無書法研究社へ。
まあ、付け焼刃なのはしょうがないし、地力がないのもしょうがないので、随分拙いものをお見せしてしまった感じで反省する事しきりで….がんばるぞ、おー。
帰宅は16時、そこからばったり爆睡….明日は仕事だっちゅうの…..
ゴールデンウイーク二日目も書道三昧だったこと
2011年4月30日 書道昨日は22時には、ばったり死んだように寝てしまったので、目覚めは5時…..習慣とはいえ、あんなにつかれてたのに、自分でも良く起きれるもんだなと思う。今日は12枚は書きたいと思うけれど、僕の場合、書くのが遅くて一枚書くのに30分近くかかるから、単純に集中している時間だけで6時間はかかる….ってことは、やっぱり10時間は見ないといけないなあともう。
熱いシャワーを浴びて、休日用のコーヒー(今日はカメルーンロングベリー)をいれ、まずは日課の臨書を2枚ほど。
気合を入れすぎても長続きしないので、先日買ったいきものがかりの『いきものばかり』をかけて落ちつきながら、じっくりと。
途中で教室で吊るし、母師匠に見ていただきながら、紆余曲折試行錯誤抱腹絶倒ののち、なんとかある程度の品質で数を書きあがったのが夜中の2時…..やれやれだぜ。
普段余りかけない分、書道養成ギプスをはめなきゃいけない期間が必要なんだけど、書きすぎで肩がいたくて動かない。つくづく若くないなあと....実感、這っていって死んだように床に入る感じで
熱いシャワーを浴びて、休日用のコーヒー(今日はカメルーンロングベリー)をいれ、まずは日課の臨書を2枚ほど。
気合を入れすぎても長続きしないので、先日買ったいきものがかりの『いきものばかり』をかけて落ちつきながら、じっくりと。
途中で教室で吊るし、母師匠に見ていただきながら、紆余曲折試行錯誤抱腹絶倒ののち、なんとかある程度の品質で数を書きあがったのが夜中の2時…..やれやれだぜ。
普段余りかけない分、書道養成ギプスをはめなきゃいけない期間が必要なんだけど、書きすぎで肩がいたくて動かない。つくづく若くないなあと....実感、這っていって死んだように床に入る感じで
ゴールデンウイーク初日は書道三昧だったこと
2011年4月29日 書道あさっては読売展むけの練成会三回目….10枚は先生のところにもっていきたいから目標は15枚と設定…..とりあえずは筆慣らしに薄めの墨で王鐸の臨書を2.6×6尺の画仙紙に3枚ほど習い、半紙で今回の作品を原寸で10セットほど通しで書いてみる。
筆慣らしはこれで終了….って、もうこれで10時間もすぎちゃっててびっくりで。
ずっと摺っていた墨は伸びを調節しながら濃度を調節するのにいい感じの濃墨になり、これで準備万端。熱めのシャワーを浴び、焙煎したてのとっておきのコーヒー(モカシダモG2)をドリップして気合をいれ、書き始める。…..気合の入れすぎで3枚でダウンしてみたり….
そいや、昨日は同僚と終電まで飲みだったよなあと…疲れてるのもあって集中力の維持が難しい。
毎日9時には家をでてほとんどはたらきづめで、帰宅は夜の10時過ぎ….その上、責任者として作品を作るテンションを毎日要求されてるから、同じようなテンションを要求される書道を帰ってきてはできないので、仕事の日には朝1時間しかできないから気持ちがあせってるんだろなあと思う。
12時間書いて…結果、全く満足いってないのが…3枚、先は長いなあと….
筆慣らしはこれで終了….って、もうこれで10時間もすぎちゃっててびっくりで。
ずっと摺っていた墨は伸びを調節しながら濃度を調節するのにいい感じの濃墨になり、これで準備万端。熱めのシャワーを浴び、焙煎したてのとっておきのコーヒー(モカシダモG2)をドリップして気合をいれ、書き始める。…..気合の入れすぎで3枚でダウンしてみたり….
そいや、昨日は同僚と終電まで飲みだったよなあと…疲れてるのもあって集中力の維持が難しい。
毎日9時には家をでてほとんどはたらきづめで、帰宅は夜の10時過ぎ….その上、責任者として作品を作るテンションを毎日要求されてるから、同じようなテンションを要求される書道を帰ってきてはできないので、仕事の日には朝1時間しかできないから気持ちがあせってるんだろなあと思う。
12時間書いて…結果、全く満足いってないのが…3枚、先は長いなあと….
読売書法展向け練成会二日目のこと
2011年4月10日 書道昨日夜中までかかって太無先生に見せるサンプル作成が終了、なれない勤務のせいもあって、疲労でとてもとても書をかけるテンションではなかったので2時間ほど仮眠を取ることに。2時半からスタートして半紙で2回ほど習い、2.6×6尺の画仙紙にむかって書きはじめる。
この時点で4時。とにかく5枚は仕上げてお見せしなければいけないので、出発する8時にはなんとしても、練成の規定枚数5枚かかなきゃいけない。なんたって、一応太華書道教室の副代表だから、ほかのお弟子さんの手前、弱音は吐けないし。前回、墨の濃度が濃すぎて穂先の動きが重くすぐ渇筆になってしまったので、墨の濃度に注意しながら。8時まででなんとか5枚は書いたものの、疲労のせいで内容は知れる感じで。まさに『ドロ縄』状態。
幸いサンプルのほうはいくつか注意点があったもののおおむね好評。
作品のほうは、『去年よりは良くなった、品格は出てきたけれど、もうちょっと元気に書きなさい』ということ…練成会の最中、一時間ほど抜けて車中で30分ほど仮眠。もう若いときほど体力ないなー、なんて実感してみたり。
お弟子さん解散後、印刷物の打合せと、図録用の撮影をして18時帰宅
この時点で4時。とにかく5枚は仕上げてお見せしなければいけないので、出発する8時にはなんとしても、練成の規定枚数5枚かかなきゃいけない。なんたって、一応太華書道教室の副代表だから、ほかのお弟子さんの手前、弱音は吐けないし。前回、墨の濃度が濃すぎて穂先の動きが重くすぐ渇筆になってしまったので、墨の濃度に注意しながら。8時まででなんとか5枚は書いたものの、疲労のせいで内容は知れる感じで。まさに『ドロ縄』状態。
幸いサンプルのほうはいくつか注意点があったもののおおむね好評。
作品のほうは、『去年よりは良くなった、品格は出てきたけれど、もうちょっと元気に書きなさい』ということ…練成会の最中、一時間ほど抜けて車中で30分ほど仮眠。もう若いときほど体力ないなー、なんて実感してみたり。
お弟子さん解散後、印刷物の打合せと、図録用の撮影をして18時帰宅
練成日まえの準備のこと
2011年4月9日 書道今日は昼から夜中までかけて第30回記念昌熾会展で配布する故・中野越南先生の書籍サンプルページを作る、昨日数枚の写真処理はしていたけれど、版下作成という事で結構時間がかかってしまった。表紙6パターン、裏表紙、写真ページ3ページ、カラーページとモノクロページのサンプルを2点ずつ作成。
ぜんぶで36ページのリテイク込みの画像処理は多分実作業5日、リテイク作業2日あればなんとかこなせるはず….土日、休日使って5月末くらいにはなんとかなるかなあと思う。
読売書法展の内覧会の締め切りもその辺だけど、先生の希望ということだし、会にとってはこの書籍のほうが重要だから、今月はそちらに注力することに。今月の休み、全部つかえばなんとか形にはなるかなあと思うけど…作品作りは、平日は9時から出て帰ってくるのが早くて22時だから….まあ…無理だなあと今月中はあきらめる感じで。まあ、ひとつきあれば、作品のほうはなんとかなるかなあと。
ぜんぶで36ページのリテイク込みの画像処理は多分実作業5日、リテイク作業2日あればなんとかこなせるはず….土日、休日使って5月末くらいにはなんとかなるかなあと思う。
読売書法展の内覧会の締め切りもその辺だけど、先生の希望ということだし、会にとってはこの書籍のほうが重要だから、今月はそちらに注力することに。今月の休み、全部つかえばなんとか形にはなるかなあと思うけど…作品作りは、平日は9時から出て帰ってくるのが早くて22時だから….まあ…無理だなあと今月中はあきらめる感じで。まあ、ひとつきあれば、作品のほうはなんとかなるかなあと。
11/16書道教室のこと
2010年11月16日 書道今日は早朝起きて、通信事務終了後、熱いフロあびて、濃い目のコーヒー飲んで気合を入れて、隷書とカナの臨書を。7時間ほど習って、今日は大人の教室の日なので、太華先生に見せに行くと、カナはまだまだな感じだったので、もう一時間習って再度見せに行く。
『隷書はいいとしても、カナはもうちょっとしっかり線を意識しないと』といわれてしまったので、先週、太無先生のところで売っていただいた『紀貫之高野切第一種』の拡大手本を参考に「いろは」から書きはじめてみる。課題をいただくとともに、こういった本を太無先生は弟子一人一人に古本屋でさがして安くくださるのは、ありがたいことだなあと思う。
教室では、来年2月の社中展に備えて、詩文作り、作品手本選び、手本づくりなど準備がはじまっている。ぼくも今回は4尺×8尺の横作品で2文字の木簡でと太無先生に指示されているので、ふさわしい文字をはやめに選ばなくちゃ、いけない。
夕方から夜中まで、サンプルと御見積作成
『隷書はいいとしても、カナはもうちょっとしっかり線を意識しないと』といわれてしまったので、先週、太無先生のところで売っていただいた『紀貫之高野切第一種』の拡大手本を参考に「いろは」から書きはじめてみる。課題をいただくとともに、こういった本を太無先生は弟子一人一人に古本屋でさがして安くくださるのは、ありがたいことだなあと思う。
教室では、来年2月の社中展に備えて、詩文作り、作品手本選び、手本づくりなど準備がはじまっている。ぼくも今回は4尺×8尺の横作品で2文字の木簡でと太無先生に指示されているので、ふさわしい文字をはやめに選ばなくちゃ、いけない。
夕方から夜中まで、サンプルと御見積作成
隷書にオロンピー筆はいいなと、再認識したこと
2010年11月15日 書道きょうは6時からでベランダ菜園にビニールシートで簡易の温室を作って、昼前からのミーティングに向けて企画書作り。
帰ってきて母と一服ついてお茶しているときも、なんとなく筆を新聞紙の上で動かしてこの間の隷書作品の一部をかいたり、古谷先生の作品のやベイフツの臨書をちょっとしてみたりしながら、オロンピー4号筆の使い心地をたしかめる。穂先の弾力をいかしてくるくる動かすような作品には、オロンピーはいいなと、再認識してみたり。
夕方からは営業関係や見積関係の書類作成と、作業指示。21時作業一旦終了。
きょうこれからはかなの臨書、先日太無先生に苦笑されたこともあって、カナの練習がんばんなくっちゃなあと。
帰ってきて母と一服ついてお茶しているときも、なんとなく筆を新聞紙の上で動かしてこの間の隷書作品の一部をかいたり、古谷先生の作品のやベイフツの臨書をちょっとしてみたりしながら、オロンピー4号筆の使い心地をたしかめる。穂先の弾力をいかしてくるくる動かすような作品には、オロンピーはいいなと、再認識してみたり。
夕方からは営業関係や見積関係の書類作成と、作業指示。21時作業一旦終了。
きょうこれからはかなの臨書、先日太無先生に苦笑されたこともあって、カナの練習がんばんなくっちゃなあと。
初めてのカナを先生に苦笑されてしまったこと
2010年11月11日 書道きょう午前中は昌熾会展の最後の仕上げで、集合写真と作品はがきの受注伝票作成とサンプルとして太無先生の作品をカラーの作品はがきにして10枚づつプリントアウトする。来年の第30回昌熾会展は中野越南展と併催、太華社中にも中野越南先生の作品が5点あるので、カラーのはがきに3枚ずつプリントアウトして、バッグに入れる。3枚あれば古谷先生、太無先生、印刷所といきわたるのでその辺は気配っておかないと。
午後4時に太無書法研究社にお伺いして、作品はがきカラーサンプル23枚、個別の作品はがき21セット420枚、集合写真40枚を納品、「おお、よくやったな、素晴らしい出来だ」とお言葉をいただき、一安心してみたり。これで、僕の第29回昌熾会展は終了…まず、まにあって、よかったなとおもう。作る側にも事情はあるけれど、待たされる側は一日千秋だから、ちょっと無理しても早くしておくに限るから。
太無先生に「カナを勉強しろ」って言われて思わず「え?僕がカナっすか?」って聞き返してしまってからひとつき。紀貫之の『高野切第一種』を臨書してるんだけど、ままならず、きょうは成果を見せなきゃいけないんだけど、ずっと漢字作品ばかりしてきた僕にとって、カナは鬼門…やったことがまるでないから、まあしゃあないんだけど….
まぁ太無先生の反応も、しょうがないなぁって感じで「確かに形は似てるが、形を追うことに終始してはダメだ、呼吸感をだしつつキメル所はしっかりとキメること」っていいながら何枚も拡大して、点画をかいていただいた。
なるほど、いくつか誤解があった、これを生かしてかいてみよう。
帰宅後は24時まで書類作成
午後4時に太無書法研究社にお伺いして、作品はがきカラーサンプル23枚、個別の作品はがき21セット420枚、集合写真40枚を納品、「おお、よくやったな、素晴らしい出来だ」とお言葉をいただき、一安心してみたり。これで、僕の第29回昌熾会展は終了…まず、まにあって、よかったなとおもう。作る側にも事情はあるけれど、待たされる側は一日千秋だから、ちょっと無理しても早くしておくに限るから。
太無先生に「カナを勉強しろ」って言われて思わず「え?僕がカナっすか?」って聞き返してしまってからひとつき。紀貫之の『高野切第一種』を臨書してるんだけど、ままならず、きょうは成果を見せなきゃいけないんだけど、ずっと漢字作品ばかりしてきた僕にとって、カナは鬼門…やったことがまるでないから、まあしゃあないんだけど….
まぁ太無先生の反応も、しょうがないなぁって感じで「確かに形は似てるが、形を追うことに終始してはダメだ、呼吸感をだしつつキメル所はしっかりとキメること」っていいながら何枚も拡大して、点画をかいていただいた。
なるほど、いくつか誤解があった、これを生かしてかいてみよう。
帰宅後は24時まで書類作成
第29回昌熾会展二日目のこと
2010年11月3日 書道今日は第29回昌熾会展二日目、今回は準備などをけっこうしたからか、いろんなお役はなかったので、結構のんびりと会場で作品をひとつひとつじっくりと鑑賞できたのがよかったかなあと。
夜は『木曽路』で授賞式、夜遅くに帰宅。
太無先生のお話によく耳をかたむけていると、その作品になにがあるのか、またないのかがよくわかる。経験のない僕が、『書的なクオリティ』を見出すには先人の言葉を自我(プライド)なく鵜呑みにして従うことが最重要で、また、そういった怜悧な評価の目で、言い訳なく自分の作品を常にみれなければならないと思う。
僕がいままでしてきた経験で一番役に立っているのは、作品を出すということは『不特定多数の人間を対象として言い訳のまるできかない場に、自分をさらけ出す行為』ということがしみついていること。
作品を出した瞬間に「イヤ、仕事でできなくって」「センスなくって」「体調がよくなかったから」なんてことは一切関係なく、『自己のエンターテイメントを評価』されてしまう。僕の場合、作品は、同時に商品でもあるから『未完成』であることなんかは『買い手』は知ったこっちゃない。ゲームなんか発売後に言い訳なんか絶対にきかない、大バグ出したら評価どころか、倒産、破産モノだしね。
出してるだけで満足、賞とってるだけで満足では、『芸』『文化の継承』には程遠いと感じてしまっている。
でもまあ、これはプロレベルのお話。大多数が手習い、そういったプロの意識レベルで動いているのは5%に満たないんじゃないかと思うから、仕事でもないし、マア仕方ないし、他人に話しも強要もしないけれど。
誤解をしないでほしいんだけれど、僕はゲームやCGのプロで書のプロではないし、指導者でもないのであくまで『作品』に対してこんな見方もあるんだよレベルのオハナシ。
やることもやらないで『才能』のせいにしてほしくない、それこそ自分の『才能』に申しわけないと思ってほしいなあと思う。
夜は『木曽路』で授賞式、夜遅くに帰宅。
太無先生のお話によく耳をかたむけていると、その作品になにがあるのか、またないのかがよくわかる。経験のない僕が、『書的なクオリティ』を見出すには先人の言葉を自我(プライド)なく鵜呑みにして従うことが最重要で、また、そういった怜悧な評価の目で、言い訳なく自分の作品を常にみれなければならないと思う。
僕がいままでしてきた経験で一番役に立っているのは、作品を出すということは『不特定多数の人間を対象として言い訳のまるできかない場に、自分をさらけ出す行為』ということがしみついていること。
作品を出した瞬間に「イヤ、仕事でできなくって」「センスなくって」「体調がよくなかったから」なんてことは一切関係なく、『自己のエンターテイメントを評価』されてしまう。僕の場合、作品は、同時に商品でもあるから『未完成』であることなんかは『買い手』は知ったこっちゃない。ゲームなんか発売後に言い訳なんか絶対にきかない、大バグ出したら評価どころか、倒産、破産モノだしね。
出してるだけで満足、賞とってるだけで満足では、『芸』『文化の継承』には程遠いと感じてしまっている。
でもまあ、これはプロレベルのお話。大多数が手習い、そういったプロの意識レベルで動いているのは5%に満たないんじゃないかと思うから、仕事でもないし、マア仕方ないし、他人に話しも強要もしないけれど。
誤解をしないでほしいんだけれど、僕はゲームやCGのプロで書のプロではないし、指導者でもないのであくまで『作品』に対してこんな見方もあるんだよレベルのオハナシ。
やることもやらないで『才能』のせいにしてほしくない、それこそ自分の『才能』に申しわけないと思ってほしいなあと思う。
第29回昌熾会展初日のこと
2010年11月2日 書道
今日は第29回昌熾会展初日、午前中搬入なので、気合を入れてかかる。
前日には用意はすべておわっていたので、力仕事。女性が中心だし、60歳以上のかたが多いので、必然的にハシゴの上にのぼって懸命に学生の書の展示をする。昨年と違い要領はわかってきてるので、自分たちのパートだけにとどまらず、ほかのパートのお手伝いもして一時間程度で終了。寒い日なのにもかかわらず、汗びっしょりになっちゃったので、もっていったTシャツ、Yシャツにきがえ、作品をゆっくり見ながら食事をして13時からの開場にそなえる。
今回は前回と違い、昌熾会賞という、大きな賞をいただいたので、第一室で先生、幹部の方たちと同じ展示室になるので、緊張すること、しきりで。なんせ、初めて一年…諸先輩方のチカラある書にはとてもかなわないので見劣りしないかと心配だったり。
18時に閉会すると、町田駅でおくさんと待ち合わせ、野村さん夫妻とビールとチーズで一杯。
つっかれたなぁと。
前日には用意はすべておわっていたので、力仕事。女性が中心だし、60歳以上のかたが多いので、必然的にハシゴの上にのぼって懸命に学生の書の展示をする。昨年と違い要領はわかってきてるので、自分たちのパートだけにとどまらず、ほかのパートのお手伝いもして一時間程度で終了。寒い日なのにもかかわらず、汗びっしょりになっちゃったので、もっていったTシャツ、Yシャツにきがえ、作品をゆっくり見ながら食事をして13時からの開場にそなえる。
今回は前回と違い、昌熾会賞という、大きな賞をいただいたので、第一室で先生、幹部の方たちと同じ展示室になるので、緊張すること、しきりで。なんせ、初めて一年…諸先輩方のチカラある書にはとてもかなわないので見劣りしないかと心配だったり。
18時に閉会すると、町田駅でおくさんと待ち合わせ、野村さん夫妻とビールとチーズで一杯。
つっかれたなぁと。
作品用に墨の準備をはじめてみたこと
2010年5月7日 書道先日、弓納持先生から『この調子で書いていけば良し』と言われたこともあり、今日から実際の作品作りにかかる。練習は墨汁でも良いのだけれど、作品となるとやはり固形墨を使ったほうが発色も墨の伸びも違ってくるので家にあった墨すり機(※1)で作品用の固形墨をすり、磨墨(※2)を作ることに。
いざ気合が入ったときに墨がないんじゃオハナシにもならないし。
で、濃い目の墨が欲しいので墨すり機のギッチョンギッチョンと音を聞きながら4時間ほど摺ってみると摺りすぎでドロドロ、2時間半では薄い感じがしたので3時間を1回として計5回ほど摺ってみる。一回50cc程度なので5回で250cc。これを直射日光の当たらない密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管することに。
とはいえ、10丁型12000円の『抱雲』をこれで半分消耗してしまうのは厳しい。
もうちょっと墨汁で頑張ってみるかなあ。
※1墨すり機・・・墨を磨り下ろす機械、存外に高価。
※2磨墨・・・固形墨を摺って液状にしたもの。
呉竹『抱雲』http://www.craftduo.co.jp/KWSC/GoodsInfo.aspx?ShoCd=0107003100
呉竹『墨すり機 縦横無尽 / たおやか』
http://www.craftduo.co.jp/KWSC/GoodsInfo.aspx?ShoCd=2208004001
いざ気合が入ったときに墨がないんじゃオハナシにもならないし。
で、濃い目の墨が欲しいので墨すり機のギッチョンギッチョンと音を聞きながら4時間ほど摺ってみると摺りすぎでドロドロ、2時間半では薄い感じがしたので3時間を1回として計5回ほど摺ってみる。一回50cc程度なので5回で250cc。これを直射日光の当たらない密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管することに。
とはいえ、10丁型12000円の『抱雲』をこれで半分消耗してしまうのは厳しい。
もうちょっと墨汁で頑張ってみるかなあ。
※1墨すり機・・・墨を磨り下ろす機械、存外に高価。
※2磨墨・・・固形墨を摺って液状にしたもの。
呉竹『抱雲』http://www.craftduo.co.jp/KWSC/GoodsInfo.aspx?ShoCd=0107003100
呉竹『墨すり機 縦横無尽 / たおやか』
http://www.craftduo.co.jp/KWSC/GoodsInfo.aspx?ShoCd=2208004001
読売展向け第二回目練成会のこと
2010年4月11日 書道今日は上の先生である弓納持太無先生に作品と臨書をお見せする為に町田市成瀬にある『太無書法研究社』へ。
前回、2尺×8尺の縦作品と臨書をしていったのだけれど、諸事情から今回は2.6尺×6尺の手本をいただいたこともありこのサイズの作品と臨書をお見せすることに。
臨書は半紙で60枚程度習って、このサイズでは5枚。作品は半紙で40枚程度習ってこのサイズでは3枚書いて、各々一番よいと思えるものを持っていった。
やはり何が良いかまだ判らない部分もあるので、お見せする前は緊張する。
臨書は「よく王鐸の特徴をとらえている、合格!」との言葉をいただき、作品については「臨書の特徴そのままに良くかけている」との評をいただき一安心。
…とおもいきや『作品のレベルをアップさせるので手本を書き直す』とのこと、書かれた作品は僕から見たら『これはとても、書けないだろう』と思えるような気合の入った一品。
帰宅時、若干途方に暮れていた僕を見て太無先生が「どうだね、厳しいかね?」と訊かれたので、「いや、やりがいありそうなんで、ダメもとでトライしてみます。」と明るく返してみたり。まあ、ダメでも僕の作品だし、やるだけやってみようかなあと。
前回、2尺×8尺の縦作品と臨書をしていったのだけれど、諸事情から今回は2.6尺×6尺の手本をいただいたこともありこのサイズの作品と臨書をお見せすることに。
臨書は半紙で60枚程度習って、このサイズでは5枚。作品は半紙で40枚程度習ってこのサイズでは3枚書いて、各々一番よいと思えるものを持っていった。
やはり何が良いかまだ判らない部分もあるので、お見せする前は緊張する。
臨書は「よく王鐸の特徴をとらえている、合格!」との言葉をいただき、作品については「臨書の特徴そのままに良くかけている」との評をいただき一安心。
…とおもいきや『作品のレベルをアップさせるので手本を書き直す』とのこと、書かれた作品は僕から見たら『これはとても、書けないだろう』と思えるような気合の入った一品。
帰宅時、若干途方に暮れていた僕を見て太無先生が「どうだね、厳しいかね?」と訊かれたので、「いや、やりがいありそうなんで、ダメもとでトライしてみます。」と明るく返してみたり。まあ、ダメでも僕の作品だし、やるだけやってみようかなあと。
読売展向け作品の臨書がひと段落ついたこと
2010年4月9日 書道今日は明後日上の先生に見せるための臨書を完成させる予定の日。
半紙での臨書は済んでいたので朝から2.6尺×6尺の画仙紙に向かう。
昨日までの半紙臨書がタタって右肩から手首までが筋肉痛で痛く、案の定、筆の釣り上げがうまくいかないので連綿線(※)がうまく出せず悪戦苦闘してみたり。
何枚も画仙紙をムダにして夜中までかかってようやく満足の行く一枚がかけた感じで。明日は作品のほう、何とかしなくっちゃなあと。
※連綿線・・・点画をつなぐ細い線
半紙での臨書は済んでいたので朝から2.6尺×6尺の画仙紙に向かう。
昨日までの半紙臨書がタタって右肩から手首までが筋肉痛で痛く、案の定、筆の釣り上げがうまくいかないので連綿線(※)がうまく出せず悪戦苦闘してみたり。
何枚も画仙紙をムダにして夜中までかかってようやく満足の行く一枚がかけた感じで。明日は作品のほう、何とかしなくっちゃなあと。
※連綿線・・・点画をつなぐ細い線
3/17書道教室のこと
2010年3月17日 書道今日午前中はWeb関連デザインの仕事をした後、午後は書道教室、水曜は子供中心の日。
いつ子供がくるかわかわないので、待つ間に読売展作品の字選び(※)を。
一番手はいつも元気なまなみちゃん、元気すぎるのでお姉ちゃんの作品を持ってきたのだけれど半紙がぐちゃぐちゃに、お姉ちゃんの作品は大事にしましょう。
天気がいいこともあり大輔はちょっ早で課題を終えたことにして遊びに出て行く。
かりんちゃん、さやかちゃんは集中力が高く一生懸命に手本をみながら2枚くらいで完成していく。
みのりちゃんは合格するまであきらめずにやりたがる粘り強い子で書道やりたがり。
甘えん坊で実はマメな翔太は短期間で一番の成長株、終わったあとは腕相撲とプロレスでお相手。合間に菜園のニラの植え付けを手伝ったので葱をひと束、土産に持たせてみたり。
みんなして書道が終わった後は、折り紙とか工作で、お遊びタイム。
夕方からはクラブを終えた中学生たちが来る、うち一人は発表会が近いというのでクラブ活動4時間もしてきたということであまりにも疲れてる感じで心配してしまったり。
クラブや塾、スポーツジムのあい間に書道教室、夜8時をまわって帰る女の子もいたりで近頃の子供は忙しいんだなあと思ってみたりも。冬場よりは日が長くなってきたので帰りが遅くなってもまあちょっとは安心しているんだけれどね。
※字選び・・・字の辞典から手本の元になる字を選んで配置すること。
いつ子供がくるかわかわないので、待つ間に読売展作品の字選び(※)を。
一番手はいつも元気なまなみちゃん、元気すぎるのでお姉ちゃんの作品を持ってきたのだけれど半紙がぐちゃぐちゃに、お姉ちゃんの作品は大事にしましょう。
天気がいいこともあり大輔はちょっ早で課題を終えたことにして遊びに出て行く。
かりんちゃん、さやかちゃんは集中力が高く一生懸命に手本をみながら2枚くらいで完成していく。
みのりちゃんは合格するまであきらめずにやりたがる粘り強い子で書道やりたがり。
甘えん坊で実はマメな翔太は短期間で一番の成長株、終わったあとは腕相撲とプロレスでお相手。合間に菜園のニラの植え付けを手伝ったので葱をひと束、土産に持たせてみたり。
みんなして書道が終わった後は、折り紙とか工作で、お遊びタイム。
夕方からはクラブを終えた中学生たちが来る、うち一人は発表会が近いというのでクラブ活動4時間もしてきたということであまりにも疲れてる感じで心配してしまったり。
クラブや塾、スポーツジムのあい間に書道教室、夜8時をまわって帰る女の子もいたりで近頃の子供は忙しいんだなあと思ってみたりも。冬場よりは日が長くなってきたので帰りが遅くなってもまあちょっとは安心しているんだけれどね。
※字選び・・・字の辞典から手本の元になる字を選んで配置すること。
3/16書道教室のこと
2010年3月16日 書道 コメント (1)今日は午前中、通信事務をした後は午後は書道教室、火曜日は大人中心の日。
5月14日に〆切日を迎える教書(※1)と6月初頭に読売展作品を見ることが主な内容となる。読売展の次の練成(※2)が4月11日なのでそれに向かって作品の完成度を上げる事が一番の目標となる。
皆さんは一月前から作品の準備や臨書をされているので僕の進捗が一番遅い。書道教室の合間に王鐸字典(※3)から作品に見合った字を選んでチェックしてみたり。
はるかさんの書かれた字が綺麗でびっくりしてみたりも。
※1教書・・・一年に6度ある昇段や昇級の目安としての課題。
※2練成・・・場所などを借りて一ヶ所に出展者を集め、先生とともに、集中して作品を作成すること。
※3字典・・・字を集めた字典、時代別、個人別にある。
5月14日に〆切日を迎える教書(※1)と6月初頭に読売展作品を見ることが主な内容となる。読売展の次の練成(※2)が4月11日なのでそれに向かって作品の完成度を上げる事が一番の目標となる。
皆さんは一月前から作品の準備や臨書をされているので僕の進捗が一番遅い。書道教室の合間に王鐸字典(※3)から作品に見合った字を選んでチェックしてみたり。
はるかさんの書かれた字が綺麗でびっくりしてみたりも。
※1教書・・・一年に6度ある昇段や昇級の目安としての課題。
※2練成・・・場所などを借りて一ヶ所に出展者を集め、先生とともに、集中して作品を作成すること。
※3字典・・・字を集めた字典、時代別、個人別にある。
読売展用の詩文が決まったこと
2010年3月13日 書道今日は暖かく気温が高かったので午前中はプランター菜園の整備を。
枯れたり古くなった葉を切り取り、これは下葉の風通しを良くすることで虫をつきづらくさせることが狙い。ジャガイモ、豆類の生育が悪いので敷き藁を追加して風や寒さから守ることに。化成肥料や堆肥の追加などもしてみたりで、なんだかんだで三時間ほど身体を動かしてみる。
午後は読売展向けの詩文を作成。これはただの詩文ではなく『7行6文字の40文字程度で、ひらがなが半数以上、漢字は3文字ひらがなは4文字以上連続してはならず、並べたときに面積のバランスが良い』という条件がつくわけ。で考えたのが
作り手と言う
人は創造する
苦しみと謙虚
さを友に日々
共に歩んで行
ける者の事だ
と感じる
日々暮らしの
中に物を造り
表現する喜び
がある創作を
活計とし送れ
る人生を嬉し
く思う
夕ぐれ時に光
る店先の電球
洗たく機のと
っ手黒い電柱
の匂い親父の
拳骨すぎ去り
し昭和
の3つ。実際は縦書きなんだけれどこうやって並べてみると、行単位で漢字とひらかなとが互い違いっぽくなるように配置してあったりするのが書道の詩文の特徴だったり。
一つ目は教訓めいていてイマイチ、ふたつ目はなんとなくセンスない感じなので3つ目に決定する。はじめて詩文を書いたのでイマイチ感はあるけれど。
そのあとは作品と同じサイズに変更されちゃった臨書の手本を作成。
枯れたり古くなった葉を切り取り、これは下葉の風通しを良くすることで虫をつきづらくさせることが狙い。ジャガイモ、豆類の生育が悪いので敷き藁を追加して風や寒さから守ることに。化成肥料や堆肥の追加などもしてみたりで、なんだかんだで三時間ほど身体を動かしてみる。
午後は読売展向けの詩文を作成。これはただの詩文ではなく『7行6文字の40文字程度で、ひらがなが半数以上、漢字は3文字ひらがなは4文字以上連続してはならず、並べたときに面積のバランスが良い』という条件がつくわけ。で考えたのが
作り手と言う
人は創造する
苦しみと謙虚
さを友に日々
共に歩んで行
ける者の事だ
と感じる
日々暮らしの
中に物を造り
表現する喜び
がある創作を
活計とし送れ
る人生を嬉し
く思う
夕ぐれ時に光
る店先の電球
洗たく機のと
っ手黒い電柱
の匂い親父の
拳骨すぎ去り
し昭和
の3つ。実際は縦書きなんだけれどこうやって並べてみると、行単位で漢字とひらかなとが互い違いっぽくなるように配置してあったりするのが書道の詩文の特徴だったり。
一つ目は教訓めいていてイマイチ、ふたつ目はなんとなくセンスない感じなので3つ目に決定する。はじめて詩文を書いたのでイマイチ感はあるけれど。
そのあとは作品と同じサイズに変更されちゃった臨書の手本を作成。
読売展の詩文を考え始めたこと
2010年3月12日 書道今日午前中から午後にかけてはWebページとその関連のサンプル作成。
夕方までは過去の社員PCからのデータバックアップとライブラリの作成を。
夜はお世話になっているプログラム会社の社長さんと、もと会社の同僚と三人で飲み。
どこの会社も厳しいのは時候の挨拶っぽくなってしまっているのでその辺はお互いに軽く流して状況報告や情報の交換など。そこそこに済んであとはストレス発散の場になっていったり。
同じ立場にいたことのある人間しかわからない事も苦労もあり、わかる人間にしか話せなかったりもするのでこういったときにしっかり勉強させていただくことにしていたりも。
電車での往復に『檸檬』で有名な梶井基次郎の短編集を読む、こういったモノも100円で売っているからダイソーが近くにあるのはありがたい。
昨日読売展の作品を、2尺×8尺で縦三行の漢詩のものから2.6尺×6尺の横作品で調和体といわれている漢字かな交じりの書を書くことになってしまったので臨書の手本もこれで作ることになってしまったし、そのサイズの作品の詩文も自作しなければならなくなったのでなにか純文学系のものを読んでおきたかったというのもあって。
往復につらつらとかんがえて詩文のテーマををふたつほどに絞る。
帰宅25時半、就寝26時半
夕方までは過去の社員PCからのデータバックアップとライブラリの作成を。
夜はお世話になっているプログラム会社の社長さんと、もと会社の同僚と三人で飲み。
どこの会社も厳しいのは時候の挨拶っぽくなってしまっているのでその辺はお互いに軽く流して状況報告や情報の交換など。そこそこに済んであとはストレス発散の場になっていったり。
同じ立場にいたことのある人間しかわからない事も苦労もあり、わかる人間にしか話せなかったりもするのでこういったときにしっかり勉強させていただくことにしていたりも。
電車での往復に『檸檬』で有名な梶井基次郎の短編集を読む、こういったモノも100円で売っているからダイソーが近くにあるのはありがたい。
昨日読売展の作品を、2尺×8尺で縦三行の漢詩のものから2.6尺×6尺の横作品で調和体といわれている漢字かな交じりの書を書くことになってしまったので臨書の手本もこれで作ることになってしまったし、そのサイズの作品の詩文も自作しなければならなくなったのでなにか純文学系のものを読んでおきたかったというのもあって。
往復につらつらとかんがえて詩文のテーマををふたつほどに絞る。
帰宅25時半、就寝26時半
読売展向け第一回目練成会のこと
2010年3月7日 書道今日は読売展に向けての練成ということで、昼前から成瀬にある『太無書法研究社』へ。
中学時代の担任の先生とはいえ厳しい先生なので提出には緊張がともなう。なんといってもはじめてから半年弱しか経過していない僕が、会の上級者であるセミプロ軍団と肩を並べて作品を評価されるのだからそれもひとしおで。
一人づつ作品を評価され、悪いところに手が入ったり、手本を書き直したり。母師匠が一番の古参で最後なのでぼくはその一つ前に品評される。13時に入り5時間ほど先生の運筆法、作品で評価されるポイントなどを勉強させていただく。
で、僕の番。
先生の上の先生である古谷蒼韻先生の昔母師匠向けに書かれた手本で書いていったのだけれど、作品については「良くまねてしっかり出来ているが、これは文人系の作品だから60歳を越えてからがいいだろう。若者らしくもっと大きく書きなさい。」、王鐸の臨書に関しては「しっかり練習して形を捉えている、このまま練習しなさい。」、総評では「とにかくセンスが良い。線質も墨の入り方も申し分ない。とてもはじめたばかりと思えない。」と手放しで褒められてとりあえずほっとしてみたり。
練成後はお茶も出たので、昔の先生と生徒の関係に戻って懐かしく話させていただいたりも。
帰りの車中で母師匠も随分と喜んでいてくれたみたいで僕としても一つノルマ達成。
評価が高いのは嬉しいけれど、割り引いて初心者なりに頑張った評価と考えておかないと、慢心してしまうので注意しないとなと思う。
なんせ、調子に乗りやすいもんでw
中学時代の担任の先生とはいえ厳しい先生なので提出には緊張がともなう。なんといってもはじめてから半年弱しか経過していない僕が、会の上級者であるセミプロ軍団と肩を並べて作品を評価されるのだからそれもひとしおで。
一人づつ作品を評価され、悪いところに手が入ったり、手本を書き直したり。母師匠が一番の古参で最後なのでぼくはその一つ前に品評される。13時に入り5時間ほど先生の運筆法、作品で評価されるポイントなどを勉強させていただく。
で、僕の番。
先生の上の先生である古谷蒼韻先生の昔母師匠向けに書かれた手本で書いていったのだけれど、作品については「良くまねてしっかり出来ているが、これは文人系の作品だから60歳を越えてからがいいだろう。若者らしくもっと大きく書きなさい。」、王鐸の臨書に関しては「しっかり練習して形を捉えている、このまま練習しなさい。」、総評では「とにかくセンスが良い。線質も墨の入り方も申し分ない。とてもはじめたばかりと思えない。」と手放しで褒められてとりあえずほっとしてみたり。
練成後はお茶も出たので、昔の先生と生徒の関係に戻って懐かしく話させていただいたりも。
帰りの車中で母師匠も随分と喜んでいてくれたみたいで僕としても一つノルマ達成。
評価が高いのは嬉しいけれど、割り引いて初心者なりに頑張った評価と考えておかないと、慢心してしまうので注意しないとなと思う。
なんせ、調子に乗りやすいもんでw
2尺×8尺の臨書を書いてみたこと
2010年3月6日 書道 コメント (1)今日は一日でなんとか2尺×8尺、40文字縦3行の臨書作品を書き上げなければいけない日。午前中から王鐸の書を眺めつつ母の臨書の大きさをメドにしつつ半紙で僕なりに王鐸の字を眺めつつ臨書をしてみる。午後5時には半紙の臨書を終えて、実際の紙のサイズで2枚は書きたいのでそこまで実働8時間として12分に1文字づつ習う計算なので1文字10回程度をメドに練習する。
午後5時からは実際に2尺×8尺の紙に書きはじめる。配置の目安として母師匠の臨書を横に置き、今度は自分なりに強弱をつけながら書いていく。
10枚程度しか練習できていないので、実際に書く前に1~2回程度練習をしつつ書いていくのだけれどなんとなく似ていかない。
で、21時過ぎに2枚書きあがって母師匠に選んでもらい、明日提出することに。
正直まったく自信がないのでなんとなく寝そびれて就寝は27時。
午後5時からは実際に2尺×8尺の紙に書きはじめる。配置の目安として母師匠の臨書を横に置き、今度は自分なりに強弱をつけながら書いていく。
10枚程度しか練習できていないので、実際に書く前に1~2回程度練習をしつつ書いていくのだけれどなんとなく似ていかない。
で、21時過ぎに2枚書きあがって母師匠に選んでもらい、明日提出することに。
正直まったく自信がないのでなんとなく寝そびれて就寝は27時。
持っていく作品がいきなり増えてしまったこと
2010年3月4日 書道今日午前中に母師匠から「大変なことになった」と連絡があった。
早速行ってみると、『次の日曜日に上の先生に作品をお見せするときに、作品の他に、王鐸(※1)の臨書(※2)を作品と同じサイズでもっていかなくてはいけなくなった。』ということらしい。弓納持先生は以前お会いしたときに空海をやれとおっしゃっていたのに『なぜに王鐸?』とは思ったけれど、この急場では王鐸を中心に勉強している母師匠に聞けるメリットのほうが高いのでそれはそれで良しかなあと思う。
今日は木曜日…ってことは土曜日に作品を書き上げてもっていくという僕のプランは崩れ、また同じだけの労力を『作品とは別な評価物』のために割かなくてはいけなくなった。
仕事を早めに済ませ、夕方からは臨書というからには人物像や書法(※3)をおさえておかねばならないので王鐸のことを調べる。
インターネットにはほとんど情報がないので、王鐸の法帳(※4)、王鐸の作品集、王鐸臨書で有名な村上三島先生の臨書をあさり、母親の王鐸臨書から真似しやすそうな作品を選んで2尺×8尺と半紙用の手本を作成。
手本と同じ部分の王鐸作品集を見ながら就寝。
明日には作品を作り、明後日には臨書作品ってどんなハードスケジュールなんだか。
※1王鐸・・・明と清の二朝に仕えた官吏。書家、画家でもある。
※2臨書・・・まねて書くこと
※3書法・・・書き方の特徴
※4法帳・・・そのひとの字を集めた辞書のようなもの
王鐸WIKI http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E9%90%B8
王鐸 http://homepage2.nifty.com/tagi/404.htm
早速行ってみると、『次の日曜日に上の先生に作品をお見せするときに、作品の他に、王鐸(※1)の臨書(※2)を作品と同じサイズでもっていかなくてはいけなくなった。』ということらしい。弓納持先生は以前お会いしたときに空海をやれとおっしゃっていたのに『なぜに王鐸?』とは思ったけれど、この急場では王鐸を中心に勉強している母師匠に聞けるメリットのほうが高いのでそれはそれで良しかなあと思う。
今日は木曜日…ってことは土曜日に作品を書き上げてもっていくという僕のプランは崩れ、また同じだけの労力を『作品とは別な評価物』のために割かなくてはいけなくなった。
仕事を早めに済ませ、夕方からは臨書というからには人物像や書法(※3)をおさえておかねばならないので王鐸のことを調べる。
インターネットにはほとんど情報がないので、王鐸の法帳(※4)、王鐸の作品集、王鐸臨書で有名な村上三島先生の臨書をあさり、母親の王鐸臨書から真似しやすそうな作品を選んで2尺×8尺と半紙用の手本を作成。
手本と同じ部分の王鐸作品集を見ながら就寝。
明日には作品を作り、明後日には臨書作品ってどんなハードスケジュールなんだか。
※1王鐸・・・明と清の二朝に仕えた官吏。書家、画家でもある。
※2臨書・・・まねて書くこと
※3書法・・・書き方の特徴
※4法帳・・・そのひとの字を集めた辞書のようなもの
王鐸WIKI http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E9%90%B8
王鐸 http://homepage2.nifty.com/tagi/404.htm